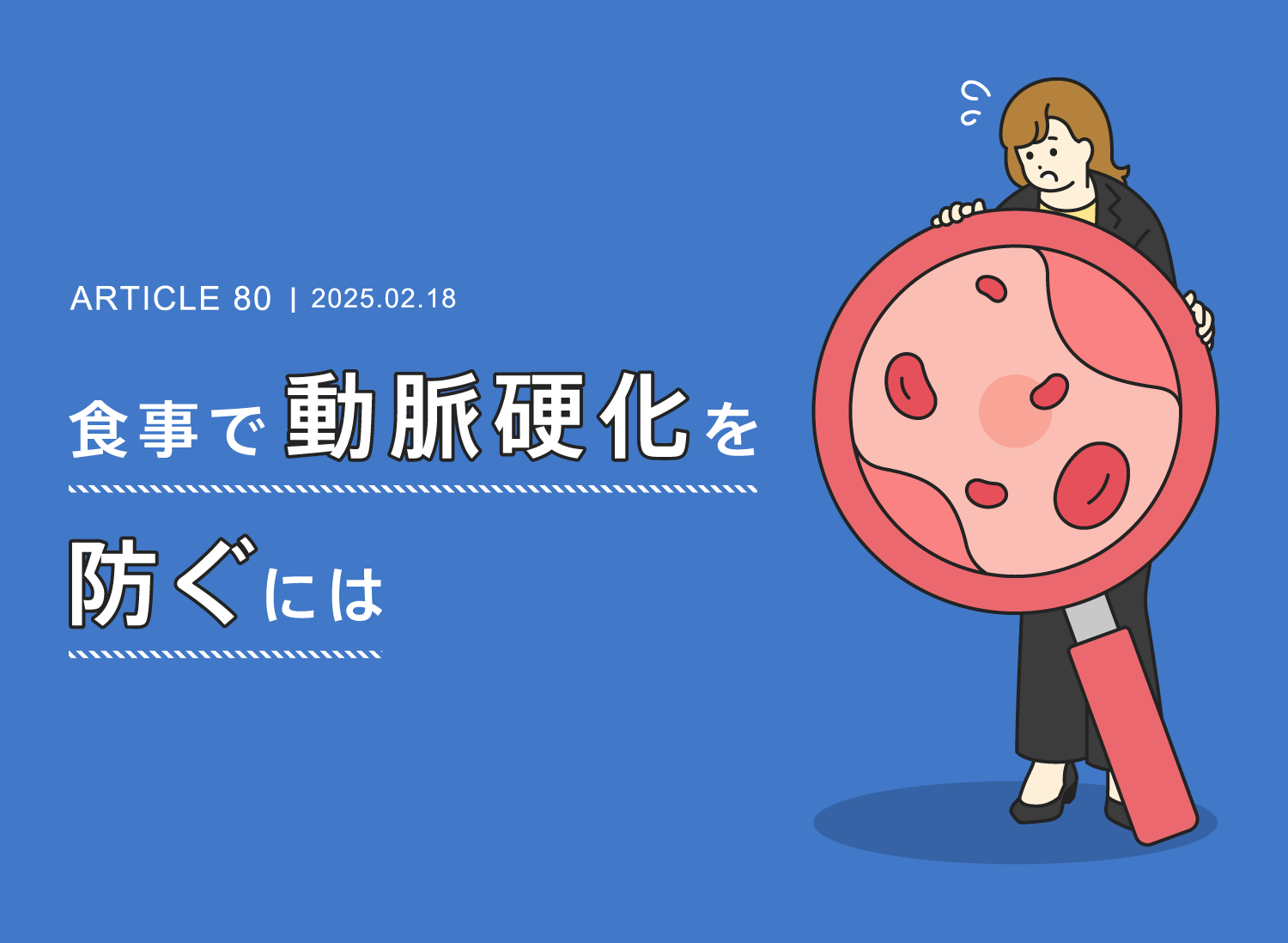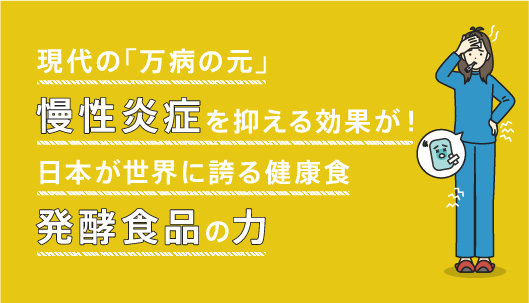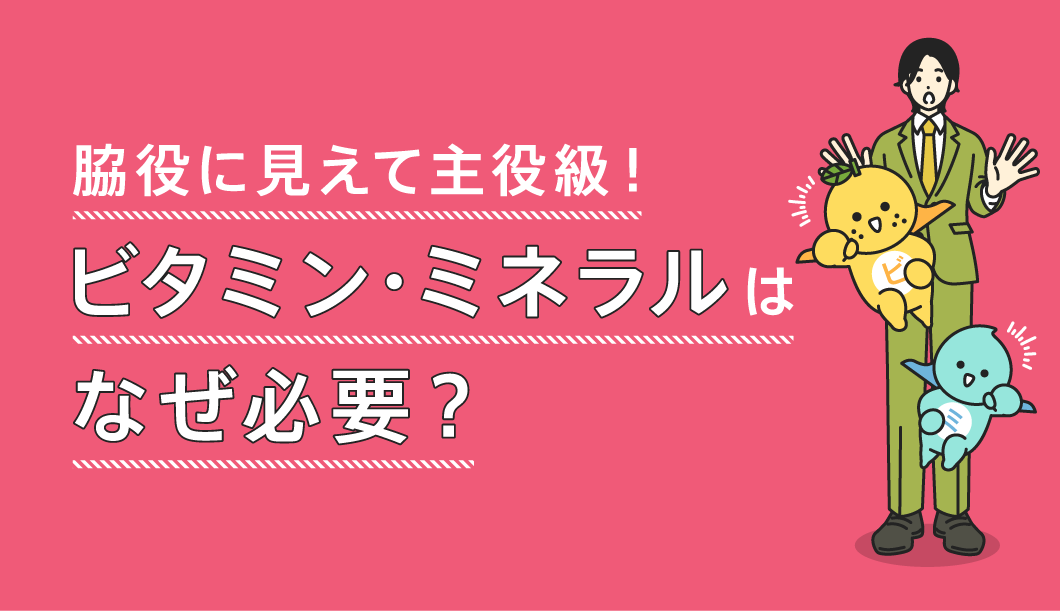動脈硬化は「炎症」から始まる
動脈硬化とは、文字通り血管(動脈)の壁が硬くなって柔軟性を失ってしまう現象です。 動脈硬化は血管の内膜で「炎症」が起こることから始まります。炎症によって傷ついた血管の内膜から炎症性細胞が生まれ、中膜へと浸潤し、血管壁が肥厚してしまうことによって、血液の通り道が狭くなります。さらに、この部分で血栓が生まれやすくなり、その先への血流障害を起こすと細胞が死んでしまいます。血栓が心臓の動脈で詰まれば心筋梗塞に、血流に乗って脳に飛べば脳梗塞につながります。このように、動脈硬化は命の危機に直結する大きな病気の原因となるため、積極的な予防が必要です。
油脂の摂り方を見直そう
動脈硬化を防ぐためには「炎症」を抑えることが重要です。その基本となるのは、適切な食事です。精製された穀類や砂糖類の摂取を控えめにし、新鮮な野菜や良質なたんぱく質を十分に摂ることで、栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。特に油脂の摂り方には注意が必要です。精製植物油(天ぷら油、サラダ油)やショートニングなどに含まれる「トランス脂肪酸」は、過剰摂取すると血管内皮の炎症を引き起こす可能性があることが指摘されています。また、植物油に含まれる多価不飽和脂肪酸のうち、オメガ6脂肪酸の過剰摂取は、炎症に関与するアラキドン酸の生成を増やすため、摂取量のバランスに注意が必要です。動物性脂肪は適量であれば問題ありませんが、動物性脂肪の多い食事に偏ると、塩分摂取も増える傾向があります。 塩分の過剰摂取は血圧を上昇させ、結果として動脈硬化のリスクを高めるため、適量を意識しましょう。一方で、炎症を抑える働きのある脂肪として、エゴマ油や亜麻仁油、魚油に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)などのオメガ3脂肪酸が挙げられます。 これらの脂肪酸には、血管の健康を維持する働きがあり、魚油や大豆たんぱくが「血管の老化を防ぐ」とされる背景には、これらの成分の影響が関係しています。
動脈硬化を防ぐ栄養素①
ビタミンD
ビタミンの中には、炎症を抑える働きを持つものもあります。その代表的なものがビタミンDです。さまざまな研究で、ビタミンDの血中濃度が高い人ほど、体内の炎症レベルが低い傾向にあることが報告されています。日本人の多くはビタミンDが不足しがちであるため、適切な摂取を心がけることが、炎症の抑制や加齢に伴う慢性疾患の予防に有効と考えられます。ビタミンDを多く含む食品には、鮭や青魚 などがあります。これらを積極的に食事に取り入れるようにしましょう。
動脈硬化を防ぐ栄養素②
ビタミンB12
また、ビタミンB12にも抗炎症作用があることが知られています。ビタミンB12は多くの細胞代謝に関与する必須栄養素の一つで、不足すると神経疾患や血液疾患などを引き起こしやすくなります。抗炎症作用があることから、痛みを訴えて病院に行くとビタミンB12製剤が処方されるのが定番ですが、高齢者では胃壁の粘膜が萎縮して吸収しづらくなってしまいます。吸収率が下がっていることも考えて、食事で多めにビタミンB12を補給することも意識するとよいでしょう。
ビタミンB12は、しじみなどの貝類、レバー、海苔などの海藻類に多く含まれています。
動脈硬化を防ぐ栄養素③
ビタミンK
もう一つ、脂溶性ビタミンの一種であり、血液凝固に関与する栄養素として知られるビタミンKも、動脈硬化を防ぎ、免疫力を維持する重要な働きをしている栄養素であることがわかってきました。
ビタミンKを補う食品の代表は、納豆やチーズなどの発酵食品と、ケールなどの緑黄色野菜です。
全身にくまなく張り巡らされた血管は60兆個もの全身の細胞に大切な栄養と酸素を届けています。この血管が硬くなって傷めば機能も低下します。体の若さを保つためにも、血管のしなやかさを保つことが大切です。これらの栄養素を積極的に補給して、動脈硬化の予防に努めましょう。
まとめ
- 動脈硬化とは、
血管の壁が硬くなって柔軟性を失う現象 - 動脈硬化は血管の内膜で
「炎症」が起こることから始まる - 「炎症」を起こさないための基本は、
適切な食事 - 炎症を抑える脂肪は
EPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸 - 動脈硬化予防に
ビタミンD、ビタミンB12、ビタミンKを
Related Article