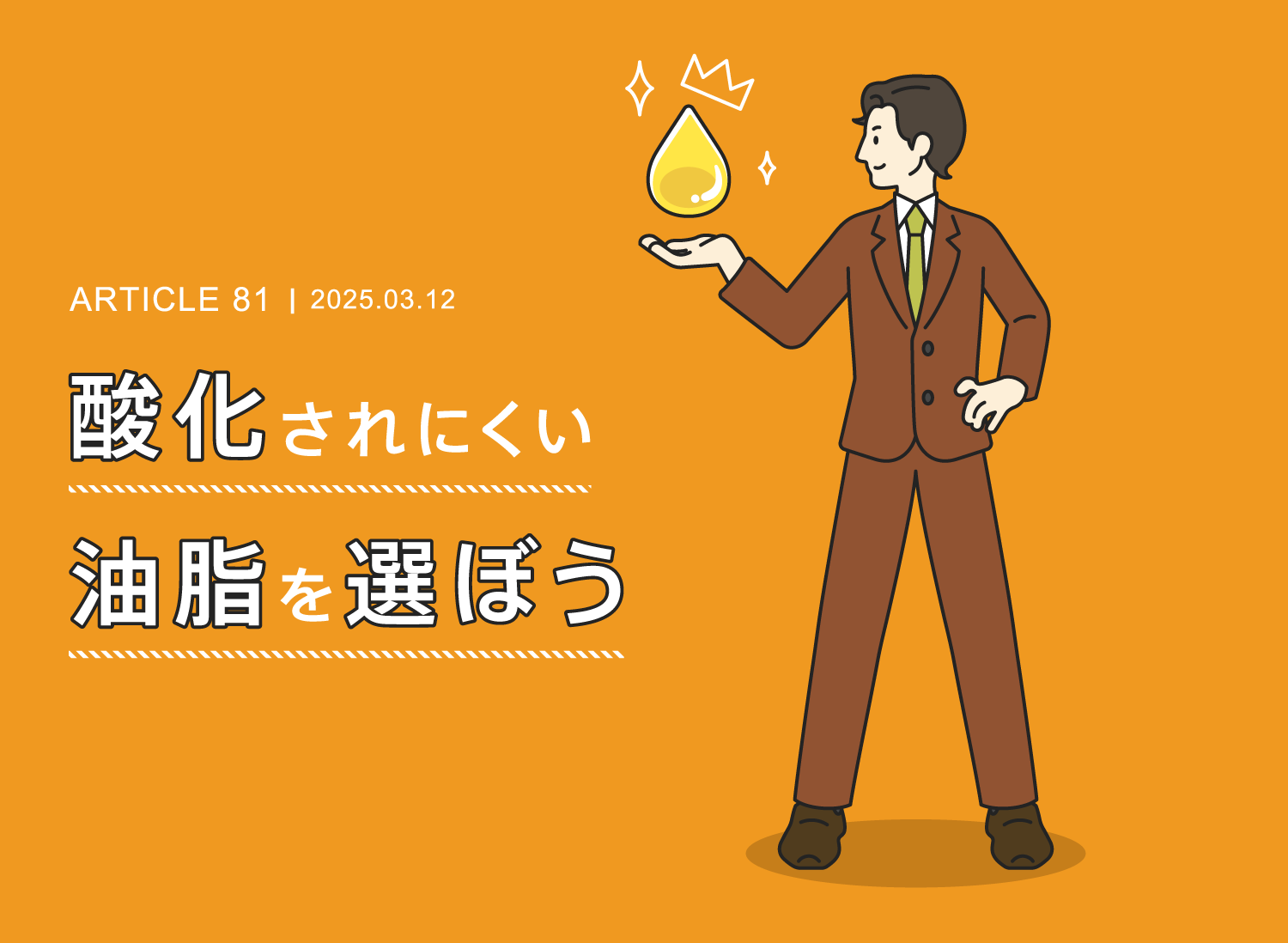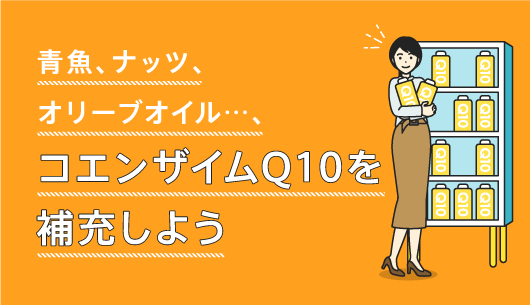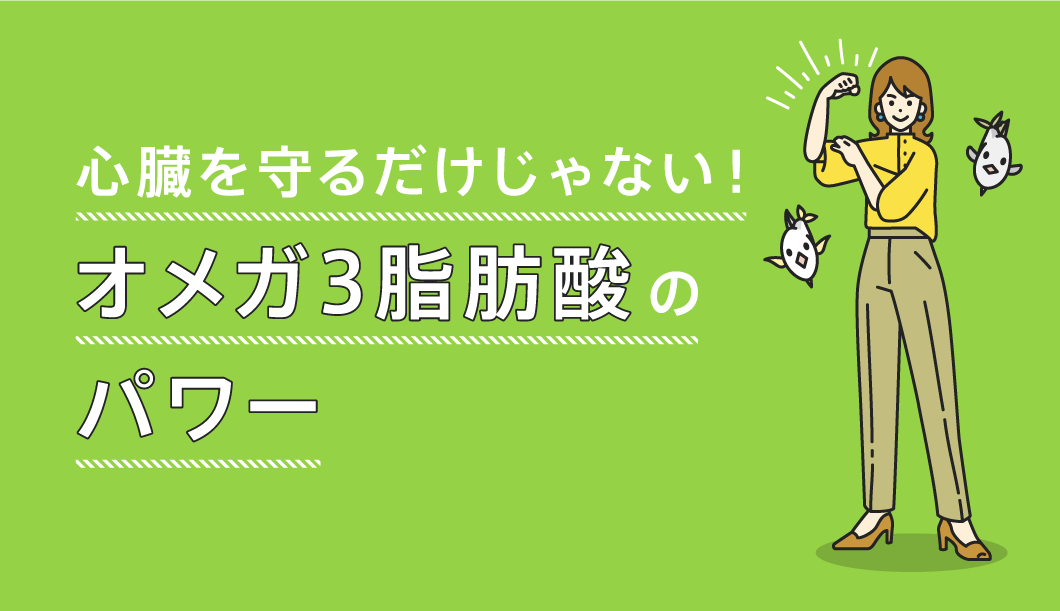油脂をわざわざ
単独で摂るのは人間だけ
油脂をわざわざ単独で摂るのは人間だけ
食用油(脂質)を選ぶとき、みなさんはどのような基準で選んでいますか。 「動物性脂肪か、植物性の油か」、あるいは「オメガ3、オメガ6」といった脂肪酸の種類で選んでいる人もいるかもしれません。 そもそも、脂質は木の実(ナッツ)や動物の脂肪など、さまざまな食品に含まれており、自然界の動物でわざわざ油脂を単独で摂るのは人間だけです。コクや風味を増して料理を美味しくする目的や、調理をしやすくする利便性などの面から油脂が使われているのだということを知っておきましょう。過剰摂取につながりやすい食用油の選び方は、とても重要です。
「酸化」は体内の老化を促進する
健康維持の観点から油脂を選ぶ場合は、「酸化されやすい脂肪酸の割合」が重要なポイントになります。 「酸化」とは、物質が酸素と反応して変化する化学反応のことです。金属が長期間空気に晒されると錆びてボロボロになるように、油も加熱や長期間空気に晒されることによって変質してしまいます。 体の中でもこれと似たような現象が起こっています。私たちの体は食べ物から取り込んだ糖質や脂質に酸素を反応させてエネルギーを作り出す際に活性酸素を発生させており、体内で増えた活性酸素が細胞を傷つけ、体を錆びさせます。酸化した油脂を過剰に摂取することは、この反応を促進し、さまざまな老化現象を引き起こすことになるのです。
加熱しても「酸化」されにくい油脂
加熱しても酸化されにくい油脂は「飽和脂肪酸(常温で白く固まる油脂)」で、代表的なものはバター、ラード、ヘット(牛脂)、ココナッツオイルなどです。飽和脂肪酸は、長鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、短鎖脂肪酸に分けられますが、中でも中鎖脂肪酸は糖質制限のサポートや認知機能の維持に役立つと言われています。中鎖脂肪酸が主成分であるココナッツオイル、MCTオイルを取り入れるのは有用でしょう。
「酸化」されやすい油脂は
加熱せずに使う
「酸化」されやすい油脂は加熱せずに使う
一方、「不飽和脂肪酸(常温で液体になる油脂)」は時間とともに酸化されやすい性質があります。不飽和脂肪酸は、一価不飽和脂肪酸(オメガ9)と、多価不飽和脂肪酸(オメガ3、オメガ6)に分けられ、植物油の中では、オメガ9のオレイン酸を含むオリーブオイルと米油が比較的酸化に強そうです。オリーブオイルについてはポリフェノール(色・苦味などのもとになる抗酸化成分)の健康効果も期待できます。
紅花油、キャノーラ油、コーン油、ごま油などはオメガ6脂肪酸を多く含む油ですが、オメガ6は現代の食生活では多くの加工食品や揚げ物に含まれるため、意識して摂取する必要はなく、むしろ過剰摂取に注意しましょう。
オメガ3脂肪酸のαリノレン酸を含むアマニ油、エゴマ油は酸化されやすい油ですが、オメガ3脂肪酸には体内の炎症を抑える働きがありますので、できるだけ加熱せずにドレッシングなどに使う、新鮮なものを少量ずつ入手するなど工夫して利用したいものです。ちなみに、魚の脂に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)・DHA(ドコサヘキサエン酸)もオメガ3脂肪酸です。魚を食べることで魚の脂を直接摂取することも大切です。
油脂の種類や性質を見極めよう
精製された植物油(天ぷら油、サラダ油)、ショートニングなどの食用油脂に含まれる「トランス脂肪酸」は、できるだけ避ける方が賢明です。トランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸に水素を添加したり、高温処理したりして油を抽出した時に生成される特殊な脂肪酸で、通常の脂肪酸とは構造が異なります。前回お伝えしたように、過剰摂取により血管内皮の炎症を引き起こす可能性など健康への悪影響が報告されています。
脂質そのものは細胞膜を作り、細胞の形や柔軟性を保つ大切な役割を担っています。肌に潤いを与える、細胞のエネルギー源になる、ホルモンや胆汁の材料になるなど体にとって重要な働きをしていますので、決して全ての脂質を控える方が良いわけではありません。脂質の量だけを問題にするのではなく、その種類や性質をよく理解して見極める目を持つことが大切なのです。
まとめ
- 自然界の動物でわざわざ油脂を
単独で摂るのは
人間だけ - 「酸化されやすい脂肪酸の割合」が
重要なポイント - 加熱しても酸化されにくい油脂は
バターやココナッツオイルなど
「飽和脂肪酸(常温で白く固まる油脂)」 - 「不飽和脂肪酸(常温で液体になる油脂)」
は
時間とともに酸化されやすい - アマニ油、エゴマ油は酸化されやすいが、
加熱せずに利用したい。
オメガ3には体内の炎症を抑える
働きがある - 脂質の種類や性質を見極めよう
Related Article